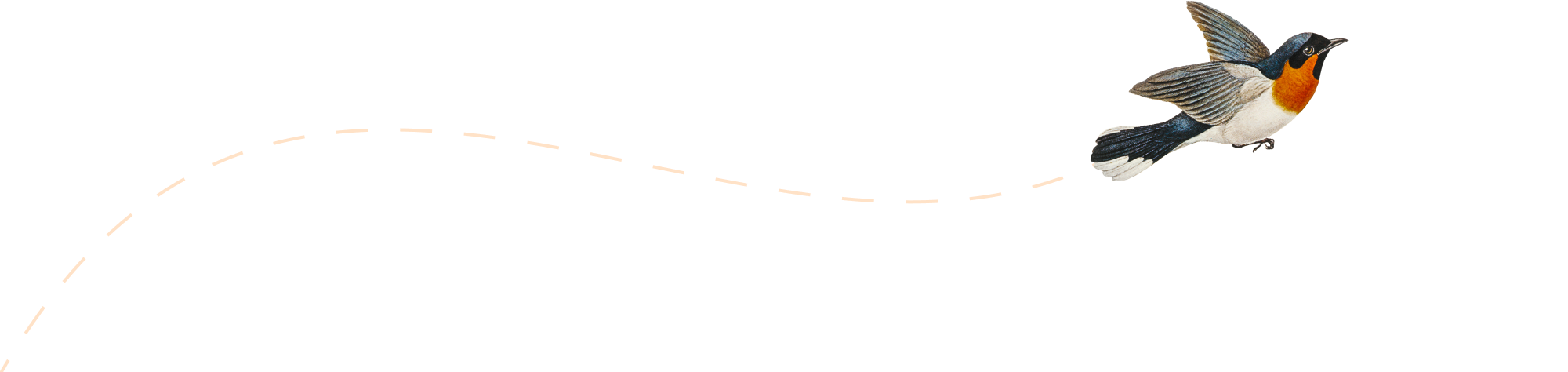-
ケーキ調達計画
本当は先週髪の毛を切りたかったのですが、予約しようと思って電話した時点ですでに予約でいっぱいだったので、今週にしたのでした。 予約した時間は11時。美容室の最寄り駅は Jungfernsteig 駅で、アパートの最寄り駅の Hasselbrook からは乗り換えなしに行けます。徒歩の時間を考えても30分くらいでつくだろうと考えて10時30分ちょっと前くらいにアパートを出たのですが … 前にもありましたが、Hasselbrook 駅と二つ先の Berliner Tor 駅の間で工事が行われているようで、S バーンが動いていません。駅の間はバスでの代行運転が行われるのですが、当然本数は電車より少ないし、時間もかかるし、で30分くらい遅れてしまいました。 しかし寒い。Jungfernsteig 駅を降りたところで気温を見たら5℃でした。アパートの中にいると暖房がかなり効いているので外の寒さは感じません。外に出て初めて気付きます。 つつがなく散髪してもらった後は、隣りの OCS で少し日本食材の買い出しを。デュッセルドルフから運ばれてくるという日本風のパン(あんパンや揚げパンのようなもの)や、レトルト食品をいくつか買い込みました。それから、以前から探して耳かきを。 昼食は先日も行ったタイ料理店「CHA CHA」へ。今日はアルコールフライではなくマンゴーラッシーを。それから、前菜としてミニ春巻、メインはマトンのカレーを頼んでみました。 マトンはサテ用にしっかり味付けしたものをカレーソースに入れたようで、カレーソースの味と喧嘩しているように思いました。ちょっといまいち。 自宅に帰って来たあとは Wandsbek 周辺へ再度買い出しに。今日のメインイベントは来週に迫った誕生日用のケーキを予約することです。以前の日記でもたびたび紹介していましたが、こちらでは自分の誕生日に自分でケーキを買ってきて振る舞います。アパートから会社までの通り道にあるケーキ屋さん(またはパン屋さん)で予約して、当日の朝引き取る、というパターンで考えていました。結局 Wandsbek にあるショッピングモール「Quarree」の中にあるパン屋さんで予約することができました。タイから来たという女の子がドイツ人の担当者との間の通訳を受け持ってくれて、何とか意思疎通できたと思います。 そういえば、今日はハロウィン。我々がすったもんだしている間に衣装をつけた子供たちが別の売り場で「Trick or Treat」をやっていました。「せえの」でみんな一緒に「Trick or Treat」のフレーズを口ずさんでいたのがとてもかわいかったです。 夕方、ちょっとうたた寝していたところでチャイムが鳴りました。なかなかチャイムが鳴ることはないので、ぐずぐずしていたら出そこなってしまったのですが、ひょっとしてハロウィンだったのかな? ***** 夜、テレビをつけてみたらワーグナーの《ラインの黄金》をやっていました。ラ・フラ・デルス・バウス(La Fura dels Baus)というパフォーマンス集団が演出を手がけた舞台のようです。指揮はズービン・メータ。以下の URL で少し写真を見ることができますが、なかなか現代的というか抽象的というか。舞台装置は最小限で、背面に投射される CG がかなり説明的な要素を担っているようです。 http://www.operaincinema.com/der_ring.htm 断片的に見ていたのですが、ラインの乙女はそれぞれ透明の浴槽の中で泳ぐは、神々たちは移動ステップのようなものに乗っているは、ローゲはセグウェイのようなものに乗っているは、ニーベルンク族の人たちはヌメヌメ気持ち悪いは、かなり賛否わかれそうな演出です。 最終部、上からワイヤーで吊るされた人たちが手足をつなぐことでヴァルハラを形作り(よくスカイダイビングのアクロバットでやられるやつを想像していただけるといいかと)、それが神々を取り囲むことで「入城」としている場面はちょっと衝撃的でした。 今後も毎月1作放映されるそうなので、忘れていなかったら(笑)見てみます。 ***** 今日のハンブルガー SV 情報。ボルシア・ドルトムント相手に先行したものの最終的には 2-3 の逆転負け。引き分けたバイエル・レバークーゼンには差をつけられ、勝ったブレーメンには勝ち点で並ばれ、得失点差で3位になってしまいました。
-
西へ
今日は本社から出張してきている海外人事関係や労働組合関係の方との打ち合わせや定期面談があって、勤務先の現地法人に行ってきました。案の定、子会社勤務の私と先輩駐在員以外はみなさんスーツ着用でした(笑)。 とりあえずの趣旨は、現在、会社の海外駐在規定の見直しを行っていて、改定案の説明と駐在員からの生の声を聞きたい、ということでした。直接的な言及はありませんでしたが、駐在地の地域差による待遇の是正にもう少しメリハリをつけようということなのかな、と思いました。要するにいわゆる先進国の待遇を薄くするかわりに、いわゆる途上国の待遇を厚くするということなのかなと。いろいろ話を聞くと、やはりハンブルクはかなり過ごしやすい土地のようです。物価もそんなに高くないですし、治安は驚くほどいいと思います。今のところ車上荒らしにあったことはありませんし、夜中の12時過ぎても普通に駅からアパートまで徒歩で帰ることができますし。まあ、もちろん、お金は貰えるのだったら貰えるにこしたことはありませんが(笑)、プライスレスな部分でも日本ではなかなか体験できないことを享受させていただいているので(いいことも悪いことも含めて)あまりガツガツしないようにしよう、と今のところは思っています。 面談をした人事の方も数年前までハンブルクに赴任されていたそうで、「僕は単身赴任だったので子供を連れて来れなかったけど、ぜひ、この素晴らしい環境をお子さんに体験させてあげて下さい。」と言われました。 さて、昼食ですが、この現地法人の社屋のはす向かいにソーセージ工場があって、そこの敷地内でソーセージスタンドのようなものが運営されています。日本人社員の方(ちなみにかしくんの同期。やっとちゃんとご挨拶できました。)に連れて行ってもらって、ここで立ち食いしました。焼きソーセージが1ユーロ、ポンメス(フライドポテト)が1.2ユーロという安さ、しかも焼きたて/揚げたてなのでどちらもおいしかったです。さすがに毎日こればっかりというわけにはいかないと思いますが … 帰りしな、中央駅付近で撮影した画像です。定かではありませんが、観光客向けに気球を飛ばしているようです。
-
新メニュー
夕食はいつものアジア料理のお店「Asia Lam」に行ってみました。 いつものように HOLSTEN のアルコールフライ、それからミーゴレン(インドネシア風焼きそば)を注文しました。 ミーゴレンは想像通りの味。エビ、鶏肉、野菜などを(ライスヌードルではなく)中華麺と一緒に炒めたものです。卵が入っているのと、香辛料をそんなに効かせていないので、サーブされたままではそんなに辛くありません。付け合わせのペーストというかチリソースというか、みたいなものを混ぜながら辛さを調節して食べます。 前回来た時に新メニューがどうのこうのという話を聞いていたのですが、今日行ってみたら「SUSHI BENTO」なるメニューがあって、おばちゃんに「これ、始めたの(推測)」みたいなことを言われました。上のビールの画像にもちらっと内容が書かれているのですが、計13個の寿司で8.90ユーロというのはかなり安いような気がします。スーパーマーケットで売られているパック入りの寿司が確かそのくらいの値段だったような気がするので、クオリティ的にちょっと不安がよぎりますが … 日本人としては一応食べてみてコメントしたい(コメントしなければいけない)気がするので、「次に来た時に食べてみますわ。」と言ったら「いつもあるわけじゃないから予約して(推測)」みたいなことを言われました。出来合いのものではなさそうなのでちょっと安心したのですが、電話して予約するというのはちょっとハードルが高いです … まあ、タイミングが合えば … という感じでしょうか。週に一回くらいはこのお店に行くことにはしているので。
-
I’m down
ええと、たまに発症するのですが、寝違えたのか、肩こりが悪化したのか、朝から偏頭痛。 例の「辛い辛いミーティング」はあまり出番がなかったので問題なかったのですが、自分のデスクで仕事をしていたらかなりしんどくなってきました。 今日は早めに帰って、鎮痛剤を飲んでひたすら寝てみることにしました。
-
グバッ・ドビュッ・ボブッ
さて、そろそろたがが外れてきました(笑)。amazon.de で買ったもの。 Gubaidulina: Am Rande des Abgrunds; De Profundis; Quaternion; In croce Sofia Gubaidulina: ‘Stimmen… Verstummen’, Symphony in 12 movements; Stufen 先日聞きに行ったグバイドゥーリナの作品展の復習用として。7つのチェロと2つのアクアフォンのための《破滅に瀕して》、12楽章の交響曲《声 … 沈黙 …》が収録されている CD です。やはり、空間芸術としての生演奏のダイナミズムを CD で体感するのは難しいですね。特にグバイドゥーリナの作品にはそういう傾向が顕著だと思いますので。 Orchestra Works 先日買ったヤンソンスのラフマニノフ交響曲全集/ピアノ協奏曲全集に入っていたカタログを見て欲しくなったので買ってしまいました。マルティノン/フランス国立放送管弦楽団&パリ管弦楽団が録音したドビュッシーとラヴェルの管弦楽作品集8枚組です。全集ではないような気がする(純粋な管弦楽作品としては全集なのかな?)のですが、主要な作品はこれでほとんど聞けるので問題ないと思います。実はドビュッシーの交響詩《海》というと、このマルティノン/フランス国立放送管の演奏が刷り込まれています。最初に買った LP (CD ではない)はアンセルメ/スイス・ロマンド管の演奏で、それはそれで悪くなかったのですが、アンセルメの柔らかな輪郭を持つ録音と比べて、マルティノンの録音はエッジの立った、かなりアグレッシブな演奏です。最近の録音とは違う、ちょっと前時代的なバランスのサウンドが、実はこの作品の持つ色彩感をうまく引き出しているような気がします。その昔、ドビュッシーはマルティノン、ラヴェルはクリュイタンス、が決定盤と言われていた時期がありました。マルティノンのラヴェルはどんな感じなのでしょう?ドビュッシーと同じようなアプローチだったらきっと気に入るような気がします。 ところで、このセットは8枚組でおよそ3000円なのですが、私はその昔《海》が収録された盤(カップリングはこのセットと同じです)を1枚3000円(ひょっとするとそれ以上)で買ったような気がします。現代作品はそもそもの音源が少ないのでレギュラー盤を買うしかないのですが、ドビュッシーやラヴェルのような超有名曲は廉価盤で十分に楽しめるように思います … というわけで、同じシリーズのケンペ/シュターツカペレ・ドレスデンのコンビによるリヒャルト・シュトラウス管弦楽作品集にもちょっと惹かれています。 Christmas in the Heart ボブ・ディランの最新作。ジャケットからも想像がつくと思いますが、クリスマス・ソング集です。どうしてしまったんでしょう(笑)?ディランが歌う《ウィンター・ワンダーランド》とか《リトル・ドラマー・ボーイ》とか、かなり想像しにくいのですが。 ***** 買い物メモ。いつものように「EDEKA」で買い出しをしたのですが、ちょっと気になったものを備忘を兼ねて貼っておくことにします。 パン屋で。ドイツ風のホットドッグのようなものですね。初めて見たのですが、おいしそうだったのでつい買ってしまいました。ベースになっているパンの名前、何て言ったかなあ?通常は丸く作られるプレッツェルを長くしたような形のパンです。その上に、キューリとディルのサラダ、マヨネーズ、ソーセージ、ケチャップを順に乗せ、最後にオニオンチップを山のように振りかけてあります。実際なかなかおいしかったのですが、きっとものすごいカロリーだと思います。あと、私は自宅に持ち帰って食べたのですが、通常のテイクアウトできれいに食べるには高等テクニックが必要だと思います。 それから、今のところ(… ってそんなにたくさん食べているわけではありませんが)いちばん気に入っているポテトチップスです。次に買いにいった時に忘れないように画像を貼っておきます(笑)。ナチュラルタイプ(じゃがいもを薄く切ってそのまま揚げたようなやつ)で、日本のものよりかなり薄くなっています。味もシンプルな塩味のみなので私好みです。
-
演奏会その17: ハンブルク・フィル第2回
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会は月に1回(正確に言うと同じ演目で日曜日と月曜日に2回開催されますが …)行われますが、今日は今シーズン2回目の公演です。 軽い夕食は、昨日見つけた「am Gänsemarkt」というお店で。ハンブルクではなかなかお目にかかれないケルシュを頼んでみました。「ケルシュ」と名乗れるのはケルン地方で醸造されたビールだけなのだそうです。 シュタンゲと呼ばれる、くびれのないビアグラスに注がれます。これで300mlです。(ヴァイツェンなどの)上面発酵系の酵母を使って(ピルスナーなど)下面発酵系並みの低温で熟成させて作るのだそうで、爽やかというよりは後からコクが広がってくるような味でした。 一応、軽く頼んだつもりです。グラーシュズッペ(グヤーシュ)とサラダ。やはりグヤーシュは本場ハンガリーのようにこってりとは作らないのがドイツ風なのかなあ?牛肉の細切れがたっぷり入っているので、それなりにお腹にはたまります。 軽く酔ったような気がしたので、食後にラテ・マキアートを飲んで少し落ち着けました。 2. Philharmonisches Konzert Montag 26. Oktober 2009, 20:00 Uhr Alfred Schnittke – (K)ein Sommernachtstraum Sergej Rachmaninow – Paganini-Rhapsodie für Klavier und Orchester op. 43 Dmitri Schostakowitsch – Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47 Dirigent: Dmitrij Kitajenko Klavier: Rudolf Buchbinder 会社から帰る車の中であらためて気付いたのですが、シュニトケもラフマニノフもショスタコーヴィチもロシア(あるいは旧ソ連)生まれですね。イメージされる曲想は三者三様なので全然注意していませんでした。 1曲目はシュニトケの《夏の夜の夢(ではなくて)》。今シーズンの第1回定期演奏会のメインだったメンデルスゾーンの《夏の夜の夢(ein Sommernachtstraum)》の冠詞 ein (英語だと a)を否定を表す kein (英語だと no)に変えた作品名です。こういう外国語での言葉遊びは日本語に訳すのが難しいですね。 […]
-
演奏会その16: ハンブルク交響楽団
やはり体内時計は正確です。サマータイムが終了したので今日から時間がずれたのですが、午前7時30分(昨日までの午前8時30分)に目が覚めました。ちなみに部屋の中にあるパソコン、テレビのチューナーは自動的に補正されました。炊飯器が補正しないのは当たり前なのですが、iPhone は逆に時計が1時間進んでしまいました。標準時の設定が間違っているのかなあ? 昼食はご飯を炊いて、昨日買ってきた材料でチリ・コン・カルネを作りました。「作った」とは言っても、挽き肉を炒めて水とソースの素を入れて、缶詰のキドニービーンズを混ぜて煮込むだけなので包丁すら使いませんでした。IH 調理器の火加減(IH 加減?)もだんだんわかってきました。ガスに比べて暖まるまでにかなり時間がかかって、一定の温度になってからは安定しているような気がします。 チリ・コン・カルネは想像よりスパイシー。ドイツは日本と比較して辛さが控えめなので、辛くなかった場合に備えてチリパウダーを買ってみたのですが必要なかったようです。(しかし、香辛料だけが充実していっているような気がするなあ …) ***** さて、今さらですがおさらいを。ハンブルクには3つの主要なオーケストラがあります。「主要な」というのは、ハンブルク随一のコンサートホールであるライスハレで定期演奏会を開催している、という意味です。 一つはハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団(Philharmoniker Hamburg)。ハンブルク歌劇場やハンブルク・バレエでの演奏も担っています。常任指揮者はシモーネ・ヤング。 それから北ドイツ放送交響楽団(NDR Sinfonieorchester)。北ドイツ放送(NDR)が運営するオーケストラで、通常の定期演奏会の他に、ジャズバンドの形態での演奏会、現代作品をとりあげる演奏会(NDR das neue werk シリーズ、先日のグバイドゥーリナの作品展もこのシリーズです)など多彩な活動を行っています。常任指揮者はクリストフ・フォン・ドホナーニ。 もう一つがハンブルク交響楽団(Hamburger Symphoniker)。活動の規模は上記2つのオーケストラに比べると小さいですが、独自のプログラムで定期演奏会を開催しています。常任指揮者はイギリス人のジェフリー・テイト。 というわけで、今日は初めてこのハンブルク交響楽団の演奏会を聞きに行きました。 Sonntag, 25. Oktober 2009 2. Symphoniekonzert 19.00 Laeiszhalle, Großer Saal Dirigent: Dmitri Jurowski Andreas Brantelid, Violoncello Stephen Beus, Klavier Trompetenklasse Matthias Höfs Die jungen Wilden Janáček / Sinfonietta für grosses Orchester Dvořák / Violoncellokonzert h-moll Janáček / […]
-
中学の部/高校の部
全日本吹奏楽コンクールデータベースに中学の部、高校の部の結果を追記しました。関係者の皆さん、お疲れ様でした。 また、ご指摘いただいた誤り、お寄せいただいた情報なども修正/追加してあります。お問い合わせはこちらからお願いします。
-
演奏会その15: グバイドゥーリナ作品展(その2)
午前中はまったりと洗濯をしながらちょぼちょぼと「バンド・クラシック・ライブラリー」の原稿書き。自宅や実家と Skype をしていたのであまり進まなかったのですが … ええと、どうでもいいことですがお役に立つかもしれないのでメモしておきます。実家の PC で Skype を 4.0.0 から 4.1.0 にアップデートしたらビデオが片方向しか通らなくなったそうです。最初は実家からの絵がこちらに届かなかったのでカメラが壊れたのかと思っていたのですが、別の日にはこちらの声だけが実家に届いてビデオが届かないということがありました。実家の PC は Celeron 2GHz / 2GB RAM / Windows XP SP3 らしいのですが、どうもこのスペックだと処理が追いつかないのでどちらかのビデオだけを処理しているのではないか、という結論に至りました。とりあえず Skype のバージョンをもとに戻したら解決したようです。Skype の旧バージョンは例えばこちらからダウンロードできます。 http://www.filehippo.com/download_skype/ それから、私は MacBook(何世代前だ? …)に Mac OS X と Windows XP をインストールして使っているのですが、妻によると Mac の Skype より Windows の Skype の方がビデオが安定しているそうです。ということで、できるだけストレスを減らすべく最近は Skype を使う時は Windows を立ち上げるようにしました。 午後からはぼちぼち買い出しへ。今日は曇り空ですが、何とか雨にはならずに済んでいます。明日も明後日も演奏会なので夜は外食予定です。ですので、あまり買う物もなかったのですが、ふとチリ・コン・カルネを作ってみようと思い、材料 … とはいってもインスタントのソースの素とキドニー・ビーンズと牛挽き肉だけですが … […]
-
演奏会その14: グバイドゥーリナ作品展(その1)
金曜日はカリーブルストの日 … なのですが、Dwenger の日替わりメニュー「アヒルの胸肉」がおいしそうだったので、それにしてみました。脂身が少ないけど柔らかくて、とてもよかったです、量も適度で。ヘビーメタルとワーグナーが好きな(笑)ボスと一緒に行ったのですが「来年になったら一緒にワーグナーのオペラを見に行くか?」みたいなお誘いを受けました。地元ローカルの新聞によると、今週初演されたハンブルク歌劇場の《ジークフリート》が大盛況だったそうです。生で見てみたいのですが、やはり十分に予習しないと(何年も前に DVD を買ったのに《ラインの黄金》しか見ていないし …)。 4日連続の演奏会行脚。初日はロシア生まれの女流作曲家ソフィア・グバイドゥーリナの作品展です。これは2日連続で行われる予定で、初日は管弦楽作品、2日目は室内楽作品が演奏されます。 そういえば、会場のロルフ・リーバーマン・スタジオのまわりにはあまり食事ができるところがないのです。前に行ったイタリア料理のレストランはけっこうおいしかったのですが、自宅を出たのが少し遅れたせいでゆっくり食事をするには時間がありませんでした。結局、会場内で売っていたプレッツェルとコーヒーだけ。 Freitag, 23. Oktober 2009, 20.00 Uhr Rolf-Liebermann-Studio, Hamburg Konzert 1 NDR Sinfonieorchester Leitung: Stefan Asbury Solist: Ivan Monighetti, Violoncello Sofia Gubaidulina: Märchenpoem für Orchester (管弦楽のためのメルヘン・ポエム) “Und: Das Fest in vollem Gang” für Violoncello und Orchester (チェロ協奏曲《Und: Das Fest in vollem Gang》、「そして、宴たけなわ」みたいな意味でしょうか …) “Stimmen…verstummen…”, Sinfonie in zwölf […]