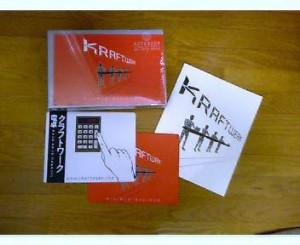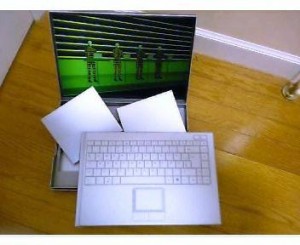ほぼ発売日に買ったまま、ほったらかしておいた(何せ時間が取れない)のであるが、 各方面からの絶賛の嵐とプレッシャーに背中を押されて、やっと見ましたとも。
 HAS/HAS HUMAN AUDIO SPONGE Live in Barcelona-Tokyo [DVD]
HAS/HAS HUMAN AUDIO SPONGE Live in Barcelona-Tokyo [DVD]
とりあえず1枚目のバルセロナ編を。
3人の並び順の配置やステージ美術などにはニヤリとさせられるが、やっている音楽は決して YMO ではなく、あくまでも HAS (Human Audio Sponge = Sketch Show + Ryuichi Sakamoto) なのだ。
基本はエレクトロニカなのだが、ラップトップをいじっているだけでなく、ちょっとずつ3人のプレーヤーとしての姿が見られるのがミソか。
YMO ナンバーである《Riot in Lagos》へのオーディエンスの反応は意外と冷静。 2枚目の東京編だとこうはいかないだろう。 このあとに名曲《Chronograph》を続けるところが絶妙。
後方のアンビエンス感が控えめではあるが、音は DTS で申し分ない。 画質はあまりよくない。